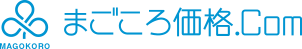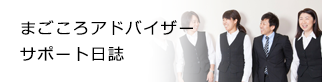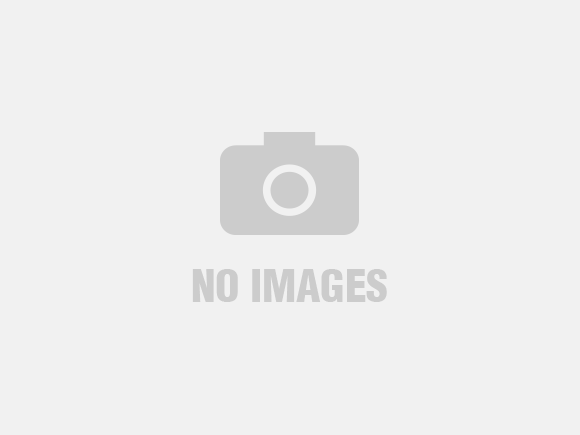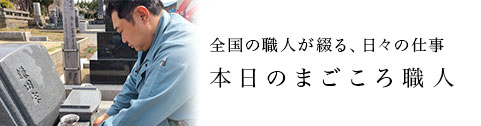前回(6月8日)では、洋型墓石でご依頼が多いデザインを
ご紹介させていただきました。
今回は、和型墓石でご依頼が多い花彫刻をご紹介いたします。
和型墓石は、洋型墓石よりも彫刻を入れる場所が限られるため、
花立が一番バランスのとれる場所だと思います。
当社人気:第3位 ゆり

当社人気:第2位 蘭(らん)

当社人気:第1位 桔梗(ききょう)

この他にも、花彫刻のデザイン例が載っているハンドブックをご用意しております。
和型墓石は、竿石正面の彫刻について書体や各宗派にあった彫刻例もご覧いただけます。
ハンドブックのご請求を、お待ちしております。
👉資料請求は、こちらから
乙部
墓石への彫刻は、家名や家紋などを入れることが多いです。
その他にもお花の彫刻を一緒にされるお客様も少なくありません。
そんなお花の彫刻の中でも、洋型墓石でご依頼が多いデザインをご紹介いたします。
当社人気:第3位 椿(つばき)と梅(うめ)

当社人気:第2位 バラとリボン

当社人気:第1位 さくら

この他にも、花彫刻のデザイン例が載っているハンドブックをご用意しております。
ちょっと覗いてみたいなと思ったかたは、ぜひ資料請求を!!
お待ちしております。
👉資料請求は、こちらから
乙部
日本には神社がコンビニの数も超えて約8万社あるとされています。初詣、七五三、など何らかの形で神社にかかわったことがあり、神道を宗教として信仰されている方も多くいらっしゃいます。
しかし神道のお墓参については仏教に比べて情報が少なくわかりにくいと思います。そこで今回は神道のお墓についてご説明いたします!
神道とは?

日本では、八百万(やおよろず)と言われるように1つではなく無数の神がいると考えられていました。その信仰に大陸から伝来した仏教、道教、儒教などが影響してつくられた日本独自の宗教です。特徴としては信仰の対象をシンボル(対象物)によってあらわしました。例えば、山や岩などの自然物。または鏡や剣などの人工物も対象となりました。
神道のお墓
神道の祭祀を行う場所が神社ですが、神道では死は穢れ(けがれ)とされているので、一般的には、鳥居の内側や敷地内に墓地は所有していません。
※所有している神社もあります。
そのため、お墓を建てる場合は、寺院墓地や公営霊園などで墓地を取得する必要があります。
神道のお墓の特徴

神道では焼香を行わないので「香炉」がなく、玉串(榊)を奉げるための「八足台(はっそくだい)」という台があります。また神道式の墓石の特徴としては、「兜巾(ときん)」と呼ばれる墓石の頭がとんがった形にすることが多いです。
この形は、三種の神器の一つである「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)」を表したものであると言われています。
また、彫刻も仏教徒は違い「○○家之奥都(津)城」と彫刻します。
神道式のお墓参り

仏教ではお墓参りのときに花を供えますが、神道では「榊(さかき)」の枝をお供えします。
また、線香は使わずロウソクを灯し、「玉串(榊)」や「神饌(しんせん)」を捧げます。
回忌じゃない?
神道の場合は「回忌」ではなく「式年祭」と呼びます。また、仏教では1周忌、3回忌、7回忌、13回忌と法要をされる方が多いですが、1年祭、3年祭、5年祭、10年祭と進んでいきます。
以上、ご説明したように仏教と神道ではお墓の形式が少し違って参ります。お墓を建てる際はお気を付けください。その他お墓に関してご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
終活カウンセラー
お墓ディレクター
本間一彰
先日、お客様から墓誌に法名を追加したいんだけど「尼」の文字が小さいのは何故?間違いじゃない?ととご質問をいただきました。私たちはお墓という仕事をしていますので、普通のこととしてとらえますが初めてお墓を建てる方はわからないですよね。そこで今回は「尼」についてご説明させていただきます。
法名と呼ぶのは浄土真宗
釋・釋尼(しゃく・しゃくに)は浄土真宗のみで使われます。通常は釋○○という具合に、釋の次に2文字つけることになります。釋は男性、釋尼は女性というように男女で別々です。ちなみに釋・釋尼の上のクラス(クラスという表現は間違ってますが、わかりやすいように表記しています)には院釋・院釋尼という院号がついたものがあります。なお、「釋」という文字は、お釈迦様の釋のことでお釈迦様の弟子になるという意味があります。
「尼」の文字が小さいのは何故?
特別な意味は無いようです。単純にこの法名は男性なのか、女性なのかを表す文字として「尼」が使われてきました。ただ、近年は男女の性別を分別もしないという考えから、女性であったとしても「釋」のみを使用するケースが増えているようです。
まごころ価格ドットコムでは基本的には「尼」の文字を小さく彫刻いたしますが、大きく彫刻してほしいとの要望がございましたらお気軽にご連絡お申し付けください。
まごころ価格ドットコム
本間
お盆でお墓参りに行かれた方も多いのではないでしょうか。
墓石の正面には、さまざまな彫刻がされています。
「○○家先祖代々之墓」の他に、「南無阿弥陀佛」のように宗派に合わせて、お題目を彫刻されているお墓も多くあります。
宗派ごとのお題目
・浄土宗・・・南無阿弥陀佛
・浄土真宗・・・倶會一處(くえいっしょ)、南無阿弥陀佛
・禅宗(臨済宗・曹洞宗)・・・南無釋迦牟尼佛
・日蓮宗・・・南無妙法蓮華経(ひげ文字-筆端をひげのように長くのばして書かれたような書体)
・日蓮正宗・・・妙法蓮華経(ひげ文字)
・神道・・・先祖代々之奥津城(奥都城)
・天台宗・・・南無阿弥陀佛
・真言宗・・・南無大師遍照金剛
などさまざまです。
ことばやお花の彫刻
宗派ごとのお題目をご紹介いたしましたが、必ず彫刻しなければいけないという決まりごとはございません。
最近では、「絆」や「ありがとう」などのことばと一緒に、お花の彫刻をお入れする方も多くいらっしゃいます。
彫刻の内容で、お墓全体のイメージも大きく変わってきます。
ご希望をお知らせいただければ、ご依頼の彫刻をお入れした完成予想図をお作りしております。
彫刻について、ご希望やご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。
太田