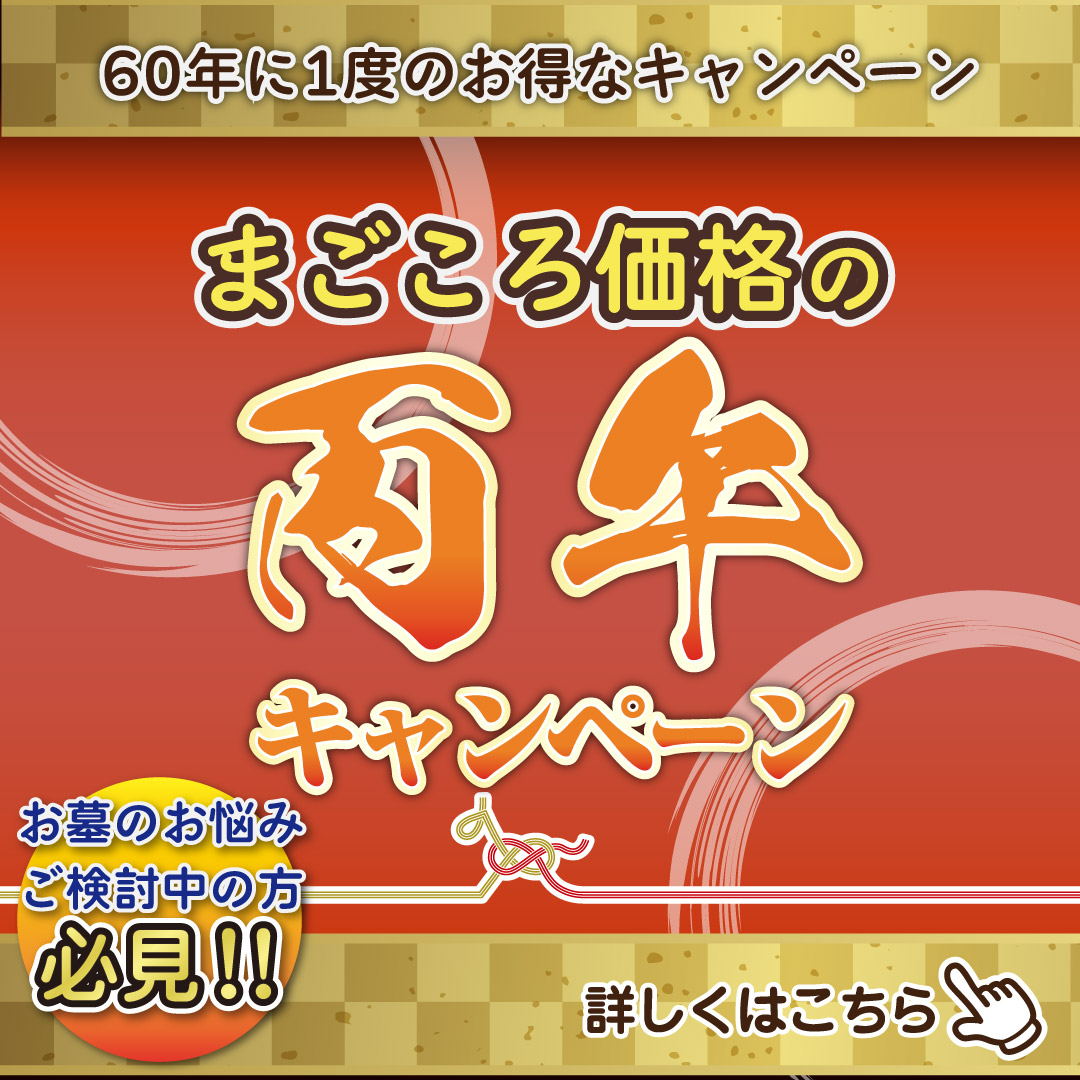そもそもお布施とは?お布施の内訳を知っておこう
お布施は葬儀のときはもちろんのこと法事・法要の際にも渡すものです。
お布施には明確な料金などの設定がありません。
そのため初めての場合にはどれくらい渡すのが適切なのかわからない人は多いでしょう。
お布施の疑問を解決するために、まずお布施とはどういうものか知っておく必要があります。
お布施は確かにお坊さんに支払うものですが、費用とは違うものです。
読経や戒名をいただく際の謝礼という考え方をします。
明確な料金として提示されないのはそのためです。
お布施の金額について「お気持ちで」というような言い方をする人もいますが、まさに気持ちで渡すものがお布施と覚えておきましょう。
ただし、そうはいってもあまりにも低い金額では失礼になります。
そこでお布施にはどんなものが含まれるか知っておく必要があります。
お布施は葬儀のときであれば、おおよそ30〜50万円の間が多く、これが一般的な相場と考えていいでしょう。
もちろん、地域によっても葬儀の規模によっても金額は異なります。
あくまで失礼のない金額ということです。
葬儀でのお布施の内訳は戒名代や読経代、それにお車代などになります。
戒名にはランクがありますが、位が高いほどお布施の額も上がります。
そしてお車代、お膳料がなどが含まれます。
また、葬儀で渡すタイミングは最初の読経から通夜、葬儀と進んで一通り終わったときにまとめて渡すのが一般的です。
お車代は例えタクシーを手配した場合でもお布施に含めるようにしましょう。
納骨式でも法事・法要のときでも、お膳代やお車代は費用をそのまま渡すのは失礼です。
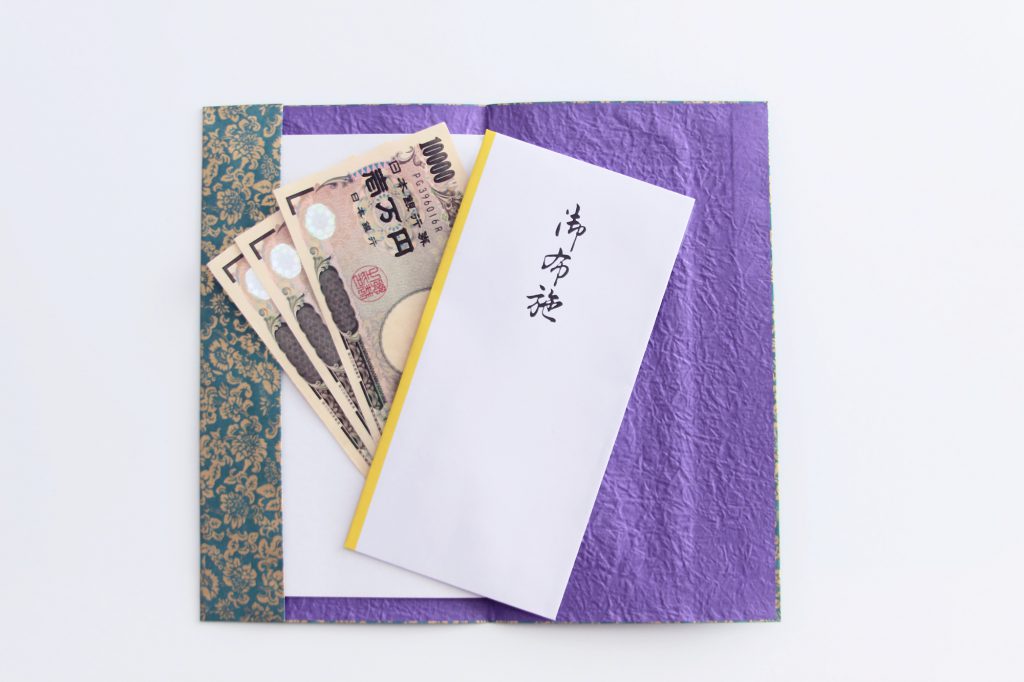
納骨式で必要なお布施の相場は?金額の決め方は?
葬儀の際のお布施はその大半を戒名代が占めているということもあり、その後の法事・法要のお布施などはかなり低くなります。
納骨式の場合のお布施の相場は大体読経が3万円ほどと考えておけばいいでしょう。
これにお車代として5000円から1万円を乗せます。
食事を辞退される場合にも別途上乗せして渡してください。
ただし、はっきりした金額が分かるものでもそのまま渡すのは失礼です。
5000円や1万円といった区切りのよい金額で渡すのがマナーとされています。
納骨式のお布施にも相場はありますが、納骨式に関するものは地域によって取り決めなどもあります。
法事・法要も納骨式もお布施は相場を目安にするのもいいですが、地域の取り決めに沿う方が無難です。
また、代々続いてきた家柄で菩提寺があればそこにお願いするのが通例で、その場合は過去帳を作っていることが考えられます。
家によっては過去帳と一緒に葬儀費用からお布施に至るまですべて記録して保管している場合もあるので、あれば参考にしましょう。
または親族に相談するのも良い解決策です。
家に記録しているものもなく、親族も分からない場合はお寺に聞いても失礼はありません。
または葬儀会社に相談するという方法もあります。
お坊さんにお布施を渡すときのマナーとは?
納骨式や法事・法要でのお布施の相場が分かったところで、渡し方のマナーについても知っておきましょう。
葬儀以外の法事・法要や納骨式では読経が済んだ後にお布施を渡して特に失礼はありません。
お布施を入れる袋は地域によって慣習があるため、それに沿ったものを用意しましょう。
水引の色などもいろいろ風習が反映されている場合があります。
特に慣習のない地域なら袋への表書きとしてお布施と書かれたものでも失礼にはなりません。
自分で書く場合は薄墨ではなく普通の黒墨で書きます。
お札は袋に直に入れず、中袋を使いましょう。ない場合は半紙などで包めば大丈夫です。
ここで注意したいのが渡し方です。
直接手で渡してはいけないことになっています。
最も好ましいのは、祝儀盆に乗せて両手で差し出すという渡し方です。
ない場合には弔事用のふくさを代用してもかまいません。
その場合は渡すときにふくさから取り出し、ふくさの上に乗せて両手で渡すのがマナーです。
葬儀や法事・法要にともなう細かいものはなかなか用意できないこともあります。
揃えるといっても普段は使わないものなので失礼のないもので代用するといいでしょう。
仏教と神道でも違う!分からないときには聞いてみる
ここでは仏教式のやり方で書いていますが、家によっては神道式のところもあります。
神道式になると仏教式とはなにかと異なる部分が出てきます。
葬儀全体にかかる費用には大きな差は見られないようですが、納骨式を行うタイミングやお布施の相場やマナーなど細かい部分が異なるので注意してください。
納骨式は仏教式の49日ではなく50日で行います。
お布施も玉串料と表書きが変わるので失礼のないようにしましょう。
一般的に神道式で行う場合は代々そうしている家が多いものです。
家がどのようにしていたか分からない場合は神職にたずねてみましょう。
弔事に関わるものは家の慣習や地域ごとの風習などで細かく異なってきます。
納骨式は家族または親族など限られた人で行うことも多いですが、誰を呼ぶかといったことから決まりがある場合もあります。
葬儀自体が家族葬などシンプルなものが増えている一方で、家族や親族に限らず知人や近隣の者まで参列して納骨式を行う地域も見られます。
仏教式の場合も宗派で異なる部分は出てきます。
お布施以外の費用については葬儀会社に相談するのもいいでしょう。
分からないことは直接お寺に聞くのも良いことです。
分からないことを適当に対応して失礼になるより聞いてしまいましょう。
菩提寺があれば代々どのようにしてきたかを把握してくれていると考えられます。
納骨式はひとつの区切りです。
遠方で暮らしている場合など、その後の墓参りなどが困難な人は納骨式や法事・法要を機に墓のあり方を考えてみるのもいいかもしれません。