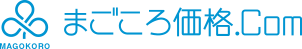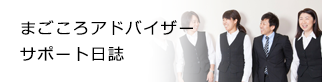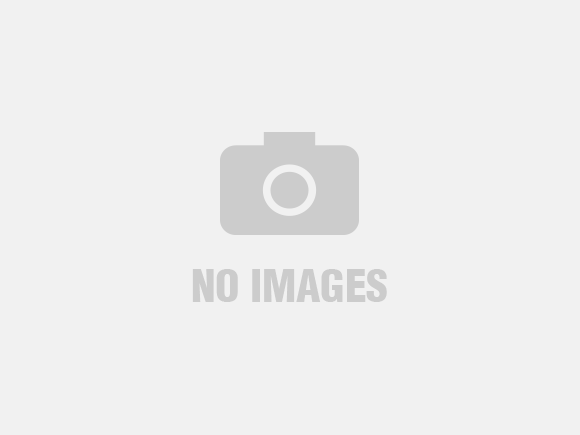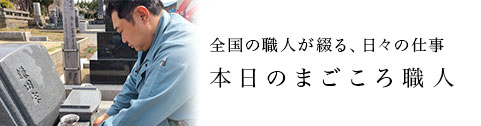本日は兵庫県西宮市にある白水峡公園墓地のお墓づくりをご紹介いたします。

まずは外柵から石材用ボンドとモルタルを使用してしっかりと石材を据え付けていきます。


石材の隅々にはサビに強いスンレス製のL字金具を使用して石材同士しっかりと固定します。


石材の重なる部分には免震シートを使用します。地震の揺れを軽減して大切なお墓をお守りいたします。


まごころ職人が丁寧に施工したお墓が無事完成しました。
「ロゼ」というデザインで洋型のお墓の中でもスタンダードなデザインです。どっしりとした竿石は多くのお墓の中にあっても存在感十分。彫刻スペースは広く幅がありお花なども彫り込むことができます。お客様の要望に合わせ多種多様なデザインを提供することが可能です。
※個人情報保護の為、お名前のわかる文字彫刻は画像処理で消しています。
本日は秋田県由利本荘市にある寺院墓地のお墓(基礎工事)づくり
<基礎工事着工前>

基礎工事着工前の状況です。本日もまごころ職人が丁寧に基礎工事を開始いたします。お墓づくりの工程
<根掘工の状況>

まずは根掘工を行います。通路面から約30センチ程掘り下げます。
<転圧工の状況>

次に転圧工を行います。根掘工の後、10センチ程の砕石を敷き詰めてランマー等でしっかり踏み固めます。このように踏み固める事で基礎地盤を強化します。
<配筋工の状況>

次に配筋工を行います。コンクリートのひび割れを防ぐ為、約20センチ間隔で鉄筋を組んでいきます。
<生コン打設工完成>

生コン打設工を行います。コンクリートを流し込みバイブレーターで振動を与えて締め固めます。最後に、表面を丁寧にコテで均してきれいに仕上げます。コンクリートが乾くまで一定の養生期間をおいて基礎工事の完成です。地震でお墓が傾く事のないように地面を掘り下げ十分な数の鉄筋を配筋しています。コンクリートの強度も含め、住宅と同じような耐震基礎をつくっています。
※個人情報保護の為、お名前のわかる文字彫刻は画像処理で消しています。

本日は鹿児島県出水市下鯖町にある共同墓地にてまごころ職人が施工したお墓をご紹介します。
石積工事の工程を写真でご覧下さい。

基礎工事から数日が経過して、充分に乾いたのを確認して石積工事を始めます。
お墓の横に石材を吊るためのクレーンを設置します。通路や近隣のお墓を傷つけないよう配慮しながらクレーンの足を広げていきます。

納骨室の状況です。
お骨壷を安定してお納めできるように板石を設置しております。

ステンレス製の芯棒と金具を使用して石材同士をしっかりと留めていきます。



石材を積み上げていきます。
石材が上下に重なる部分居に、揺れを逃がす免震シートを使用し、地震対策を施しています。
ステンレル金具と免震シートを併用して、大切なお墓を地震の揺れから守ります。

マスキングテープを貼ってからシーリング剤を充填していきます。
石材同士の隙間を埋めて汚れなどが入り込むのを防ぎます。

広々とした敷地の中に、伝統的な和型のお墓が完成しました。
高さのあるデザインですが、白御影石を使用しているので優しい印象となりました。

工事の後は通路などに機会の跡を残さないよう、掃除をして帰ります。
※個人情報保護の為、お名前のわかる文字彫刻は画像処理で消しています
本日は北海道足寄郡陸別町にある公営霊園にて、まごころ職人が施工したお墓づくり(墓石工事)をご紹介します。

今回はこちらの写真の洋型墓石が出来上がるまでの工程についてご紹介いたします。


【お墓の土台(外柵)部分の施工状況】
四角い升が3つありますが、真ん中がの升が納骨室にあたる部分になります。石と石が交わる部分の重要ヵ所には錆に強いステンレス製のL字金具で補強いたします。こちらのL字金具はお墓を建てた後では確認することが出来なくなります。

【シーリング工程の状況】
石と石の間に雨水が入り込まないように、マスキングテープで養生しながら墓石用のコーキング剤を充填いたします。


【石塔設置・地震対策の状況】
地震の揺れによるお墓の倒壊を防ぐため、「まごころ価格ドットコム」では全てのお墓に免震工法の墓石用特殊ゴムマットを標準でお付けしております。黒色に見えているシート状の物がが特殊ゴムマットになります。

【お墓の完成】
お石塔には高級な黒系御影石を使用し、土台(外柵)部分には白系御影石を使用した重厚を感出しつつも、柔らかくあたたかな雰囲気包まれたようなお墓に仕上がりました。また、こちらのデザインはお参りスペース(参道)部分を広く見えるように設計されており、お掃除がしやすいのも特徴です。
※個人情報保護のため、お名前がわかる文字彫刻は画像処理で消しています。
本日は岩手県遠野市にある共同墓地にてまごころ職人が施工したお墓をご紹介します。

こちらのお墓の建て替えを行います。

古いお墓を解体しました。


今回は東北の寒冷地なので基礎を強化するため約50cmほど根堀をしました。

砕石・転圧工
砕石を敷いたら、ランマなどで転圧を掛けて地面を押し固めます。

配筋工。
コンクリートだけだと引っ張り強度に弱いため、10ミリの鉄筋を20㎝間隔で配筋いたします。

生コンクリート打設工
生コンクリートを型枠の中に流し込み、高さ調整を行います。あとは数日養生し、コンクリートが乾いたら枠を外して基礎工事完了です。


一定期間養生し基礎が出来ましたら、石積工事を行います。まずは外柵からモルタルと石材用ボンドで据え付けて行きます。

石同士の繋ぎ目には地震の揺れに備えてサビにくいステンレス製のL型金具を使用して頑丈に固定します。


石塔の石と石の間には、建設業界でも長く使用してきた免震用のブチルゴムを挟んで大切なお墓を地震の揺れから守ります。

石と石との間に雨水が入り込まないようマスキングテープで養生しながら墓石用のコーキングを行います。

完成しました。石材は桜御影とも呼ばれ人気のG488を使用しました。洋型の柔らかなイメージにピッタリです。デザインはお客様の希望に沿ったオリジナルデザインです。当社では提案出来るデザインも豊富にございますが、お客様のご要望により様々なデザインをお作りします。是非ご相談くださいませ!
※個人情報保護の為、お名前のわかる文字彫刻は画像処理で消しています。